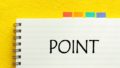「栄養学を勉強したいのですが何から勉強したらいいか教えてほしい」
私たちは日々食事からいろいろな栄養を摂っています。その栄養には身体にいろいろな影響を及ぼします。身体に良い影響もあれば、身体に悪い影響を及ぼすこともあります。
栄養学を勉強することはそれぞれの栄養を摂ることの重要さが分かるようになり、
日ごろからより健康な食事を摂ることができるようになります。
このページをご覧の方は自分や家族の健康を気にしており、栄養学を勉強したいと思っている方がおられるかと思います。
生活習慣病の予防やダイエットに向けた食事を摂りたい、子どものスポーツのための食事を勉強したい、幼い子どもに栄養のあるものを食べさせたい、高齢の親に合った食事を作りたい、
栄養学を勉強したい目的は様々でしょうが、今回お話しする内容はどんな栄養学にも通ずる基本中の基本となる「栄養を摂ることの意味は何か」についてです。
管理栄養士として働く私も、大学で初めに講義を受けた内容も「栄養を摂る意味」でしたし、
これから栄養学を勉強するときに常に頭に入れておくべきことと今でも考えています。
栄養学を独学したい方はまずこの内容を読んでいただき、栄養学をなんとなくでも理解していただけたら
今後の勉強が理解しやすくなるでしょう。
栄養を摂ることの意味は何か
栄養素の役割①「身体を動かすために必要なエネルギーの管理をすること」

ひとは生きるために身体の様々な機能を動かしています。
例えば心臓は身体中に血液を送り出すポンプとしての役割をもっていて、
私たちが意識しなくても常に動いています。
また、呼吸として身体に酸素を取り入れ二酸化炭素を排出する役割をもつ肺も、
私たちが生きるために常に動いています。
このように意識しなくても身体はそれぞれの役割を果たすために動いています(不随意運動といいます)。
また、普段生活していく中で、仕事に行く、スマホを見る、ジョギングするといったように
意識して身体を動かしながら私たちは生きています(随意運動といいます)。
これら不随意運動にも、随意い運動にも、身体を動かすためにエネルギーが必要です。
車でいうガソリンのようなもので、エネルギーがないと身体も動きません。
このエネルギーを(身体の外側から)補給する主な方法が栄養を摂ることです。
つまり、栄養を摂ることはひとが生きていく上で身体のいろいろな機能を動かすために必要なエネルギーを管理するというとても重要な意味があります。
栄養を摂るといっても、
栄養素の種類はたくさんあり、エネルギーにそのまま変えることができる「エネルギーの材料となるもの」と、
エネルギーの材料となるものを、材料の状態から代謝してエネルギーに変えるときに必要となる「エネルギーに変えるための材料となるもの」の2種類があります。
また、栄養素の中には身体の骨格や筋肉を形成したり、心臓を動かしたりといった身体の機能を維持する役割もあります。
栄養素のなかには、エネルギー管理においても栄養としての役割を持っているので、
ここでは「栄養を摂ることはエネルギー管理をすること」を知っておきましょう。
エネルギーの材料となるもの

「エネルギーの材料となるもの」として以下のものを知っておきましょう。
- 糖質
- 脂質
- たんぱく質
糖質
糖質は炭水化物のひとつで、ご飯やパン、めんといった主食、
またお菓子や果物などの甘いものに多く含まれます。
糖質は1gあたり4kcal分のエネルギーに変えることができます。
身体を動かすときにすぐ使えるエネルギーという特徴があり、全力で走ったり、筋肉を動かしたりといった動きのときに使われます。
炭水化物は糖質と食物繊維を合わせて言うときに使います。食物繊維には確かにエネルギーが含まれていますが、栄養学上食物繊維に含まれるエネルギーは無視しても問題ないので、混在しないようにあえて糖質と書いています。
脂質
脂質は肉や魚のほか、バターやごま油といったものに多く含まれます。
脂質は1gあたり9kcalと糖質やたんぱく質に比べてより多くのエネルギーに変えることができます。
特徴は持続型のエネルギーで、有酸素運動といった長い運動のときに使われます。
正確には運動をするとまずは糖質分のエネルギーが使われ、糖質分のエネルギーがなくなり始めたら次に脂質分のエネルギーを使うようになります。
脂質はエネルギーに変えるまでに時間がかかるイメージです。
(脂肪を落とすには有酸素運動を30分以上した方がいいというのはこのためです。)
たんぱく質
たんぱく質は肉や魚、大豆、乳製品などに多く含まれます。
筋肉などを形成する栄養素ですが、エネルギーの材料となる役割ももっています。
たんぱく質は1gあたり4kcalのエネルギーに変えることができます。
たんぱく質のエネルギーは脂質よりもエネルギーに変わる速さが速く、足りないときに補ってくれるイメージです。
ダイエットをして1か月で○○kg体重が落ちたということを聞きますが、
ダイエットのために普段よりもいっぱい運動したことでエネルギー必要量が増したり、食事を摂らないようにすることでエネルギーが摂れなくなったりと
急激なエネルギー不足が生じてしまいます。
その不足したエネルギーを補うのにたんぱく質が使われるので
結果的に落ちた体重は筋肉の分で脂肪はあまり落ちていないといったことになりかねません。
たんぱく質はエネルギーとしてよりも筋肉などを形成するものとして身体に使えるように栄養管理をすることが好ましいです。
ちなみにたんぱく質をカタカナでタンパク質と書く時もありますが、
たんぱく質は食事の視点で、タンパク質は学問の視点で表すときに使います。
ここでは食事の視点でお話ししているのでひらがなで書いています。
エネルギーに変えるための材料となるもの

「エネルギーに変えるための材料となるもの」として以下のものを知っておきましょう。
- たんぱく質
- ビタミン
- ミネラル
たんぱく質
たんぱく質は酵素という形でエネルギーに変えるための材料として使われる役割ももっています。
酵素とはある物質をほかの物質に変えるときに働くもので、身体には数多くの種類の酵素が働いています。
その酵素の材料となるのがアミノ酸というもので、アミノ酸が集まってできたものがたんぱく質です。
なのでたんぱく質を栄養として摂ることで酵素の材料を摂ることにもなります。
ビタミン・ミネラル
また、ビタミンやミネラルは種類が多いのでまとめて概要を紹介します。
例えばビタミンB1は糖質をエネルギーに変える代謝のなかで働く酵素をサポートする「補酵素」として働きます。
この「補酵素」は酵素の働きを活性化する効果があるので、
エネルギーに変えるときの材料としての役割を持っています。
他にもビタミンB2は脂質からエネルギーに変えるときの補酵素として
ビタミンB6はたんぱく質からエネルギーに変えるときの補酵素として
それぞれ役割を持っています。
このように野菜や果物などに多く含まれるビタミン・ミネラルも、身体のエネルギー管理に欠かせません。
栄養素の役割②「身体の機能を維持すること」

栄養素を摂る役割のもうひとつは「身体の機能を維持すること」です。
身体は食べたものから形作られています。
カルシウムという栄養素を例に見ていきましょう。
カルシウムは主に牛乳などに多く含まれる栄養素ですが、カルシウムの最も有名なイメージは骨を作る栄養素であるということでしょう。
確かに、カルシウムは身体に吸収されると骨の一部となりますので、カルシウムは骨の健康を維持するうえで欠かせない栄養素です。
ですが、カルシウムの役割は骨を形成するだけでなく、心臓を動かすという大きな役割も担っています。
このように栄養素は身体を動かすエネルギー源となるだけでなく、『身体の機能そのものを動かす』役割も持っており、栄養を摂ることは身体の機能を維持していくという生きるために重要な役を果たしています。
この「身体の機能を維持する」栄養素は、それぞれの栄養素で役割が異なるので、本サイトでは基礎編で学んでいきますので、ご参照ください。
まとめ
○ 栄養を摂ることはひとが生きていく上で「身体を動かすために必要なエネルギーの管理をすること」と「身体の機能を維持すること」の重要な役割となる
○エネルギーの材料となるものは「糖質」・「脂質」・「たんぱく質」
○身体の機能を維持するには「ビタミン」・「ミネラル」も重要
以上、「栄養を摂ることの意味は何か」について紹介しました。
このエネルギーを管理する考えは栄養管理の基本でありながら、健康を維持するうえでもとても重要な考え方です。
これを機に栄養を摂る意味を知っておいてこれからの健康管理に参考にしてください。
時間のある方はこちらも合わせてご一読ください。
栄養学を勉強するうえで必ず知っておくべき内容です。
本サイトでは栄養学を独学したい方向けに栄養学をわかりやすく勉強できる独学用サイトを開設しています。
教科書のように栄養学をまとめていきますので是非ご参考ください。